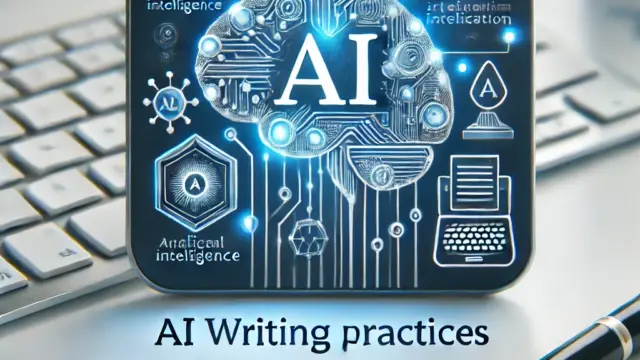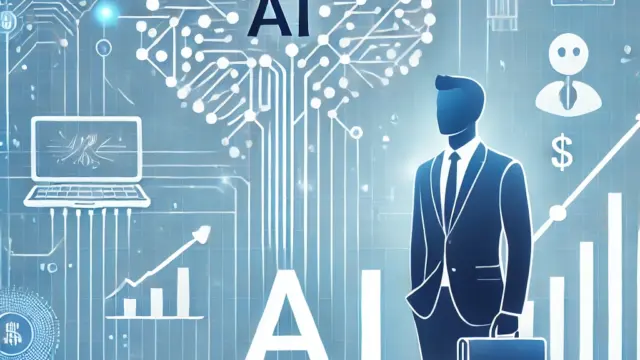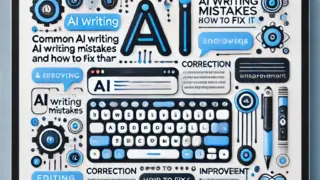AIライティングが当たり前になりつつある今、「Googleにちゃんと評価されるの?」「AIで書いた記事でもSEOで上がるの?」という不安を感じている人は少なくないでしょう。実は、その答えのカギを握るのが「E-E-A-T」という考え方です。
この記事では、ChatGPTなどのAIツールを使っている人でも、Googleから信頼される記事を書くための具体的な方法を紹介します。ブログやサイト運営で検索上位を目指すなら、必ず押さえておきたいポイントばかりです。
E-E-A-Tとは?Googleが重視する4つの評価基準
「E-E-A-T」とは、Googleの検索品質評価ガイドラインで示されている評価基準の頭文字をとったものです:
- E:Experience(経験)
- E:Expertise(専門性)
- A:Authoritativeness(権威性)
- T:Trustworthiness(信頼性)
このE-E-A-Tは、特に**医療・金融・副業など「人の生活やお金に関わる分野(YMYL)」**において非常に重視されています。
例えば、「ChatGPTの使い方」や「AIで副業する方法」などもE-E-A-Tが求められるテーマです。
AIライティングでE-E-A-Tが不足しやすい理由
AIを使った文章は、スピーディかつ効率的ですが、E-E-A-Tの観点では以下のような弱点があります:
- 経験がない: AIは自分の体験を持たないため、実体験の説得力がない
- 専門性が薄い: 情報源が不明なまままとめてしまうと、専門的な裏付けに欠ける
- 権威性がない: 書き手のプロフィールや実績がないと、信頼を得にくい
- 信頼性が低い: AIが古い・間違った情報を出力してしまう可能性も
つまり、AIの出力をそのまま使うだけでは、Googleの評価は得にくいのです。
E-E-A-Tを高めるための5つの対策
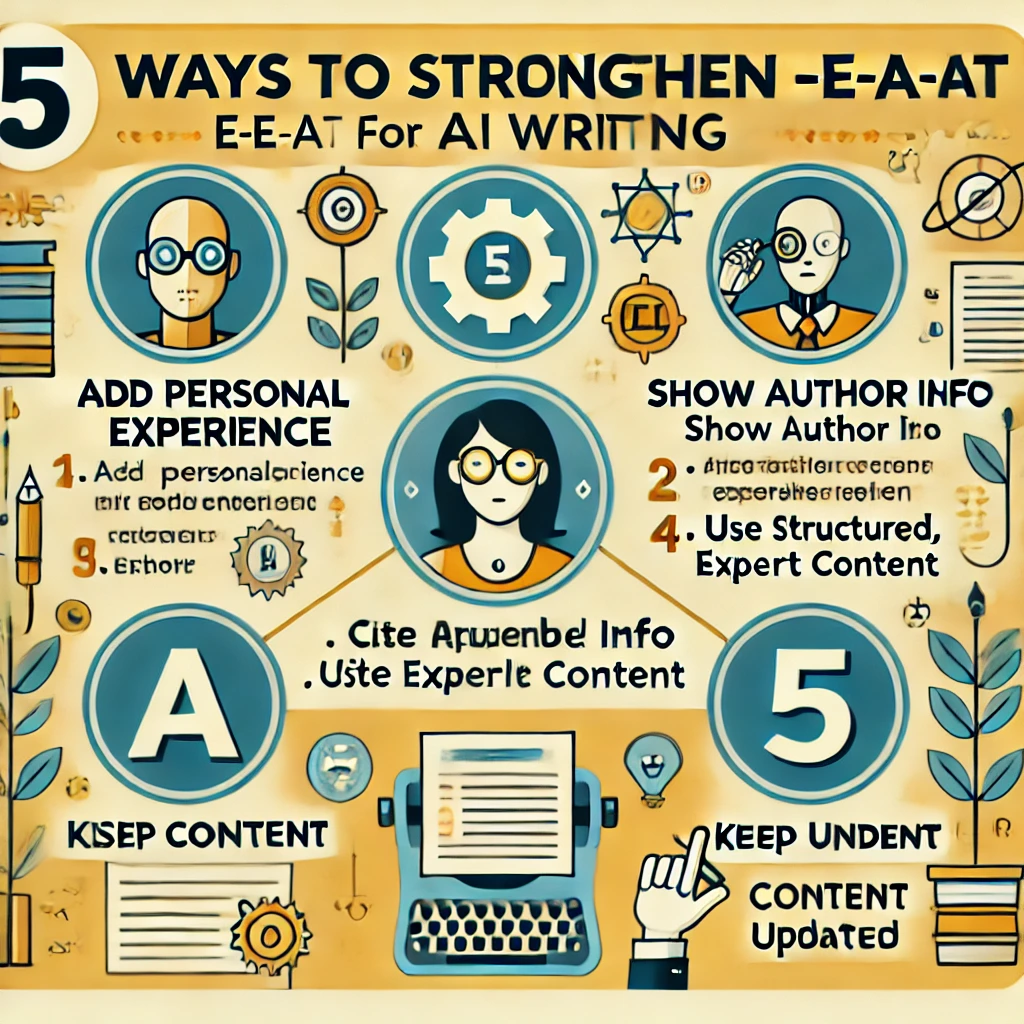
① 実体験・一次情報を加える
AIが書いた原稿に、自分の体験談や使用レビューを加えるだけで「経験」の要素が強化されます。
例:「私は実際にChatGPTを3週間使って、10記事を書きました。その結果…」
② 著者情報・運営者情報を明記する
「誰が書いたのか」を明確にしましょう。プロフィールページや記事末に著者情報があると「権威性」「信頼性」が向上します。
③ 引用・参考元をしっかり明記する
AIの回答を裏付けるために、信頼できる外部サイトや公式情報を引用しましょう。
例:厚生労働省、Google公式ブログ、OpenAI公式など
④ 専門性を高める記事構成
構成段階で「専門的な要素を含む」見出しを設定しましょう。専門用語や根拠のある情報を交えて解説するのも◎
⑤ 継続的な情報更新と品質チェック
AI記事は古くなりがち。定期的な更新と、最新情報の確認が「信頼性」に直結します。
AIを使いながらも“人間らしさ”を加えるライティング術
E-E-A-Tを満たすには、「人間らしさ」も大切な要素です。
- ストーリーテリングを取り入れる
- 感情や考察を加える
- 読者の疑問に先回りして答える
たとえば、単に「このツールが便利」と言うのではなく、「最初は不安だったけど、こんなふうに変わった」という体験のストーリーがあると、読者の共感を呼びます。
まとめ&次に取るべきアクション
- AIライティングは便利だが、E-E-A-Tの視点を忘れると評価されにくい
- 実体験・著者情報・出典明記などでE-E-A-Tを強化
- 定期的な見直しとリライトで、検索上位を狙いやすくなる
💡 まずは、過去の記事1つをE-E-A-Tの視点で見直してみましょう!
ブログは“更新するほど強くなる”コンテンツ。AIと人間のハイブリッドで、Googleにも読者にも信頼される記事を書いていきましょう。